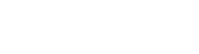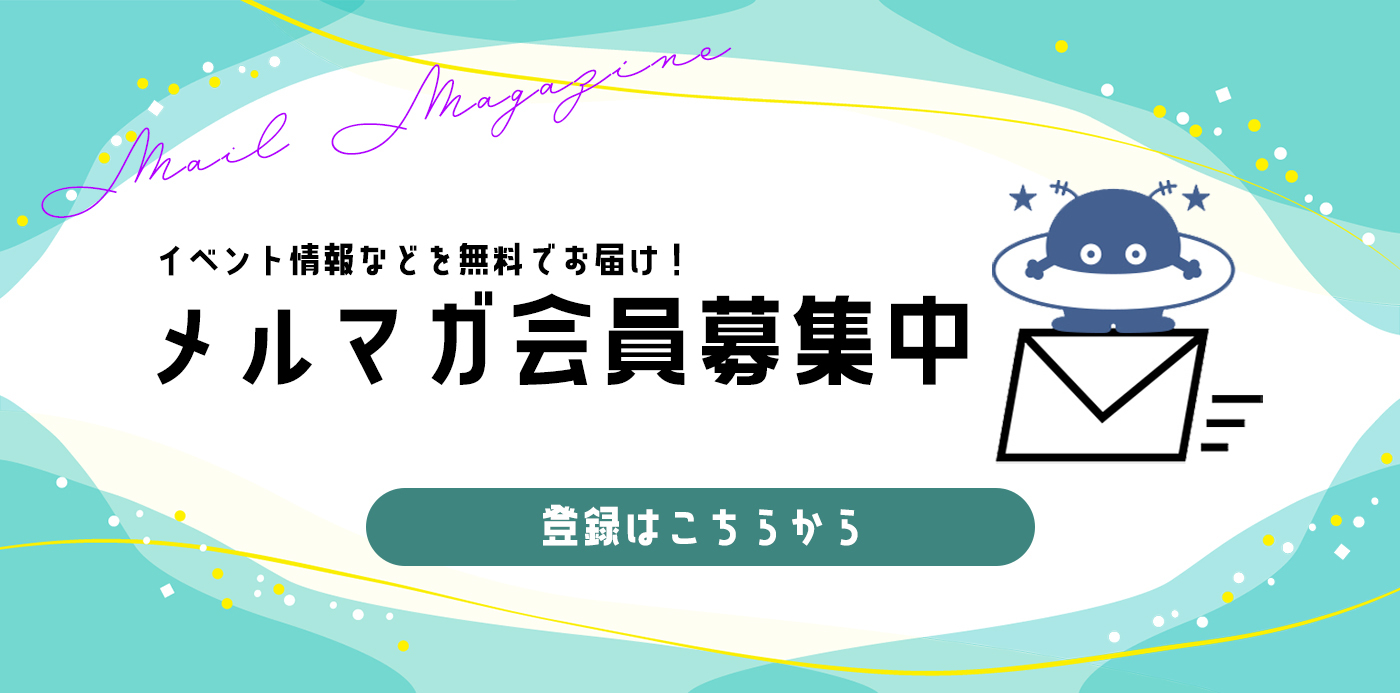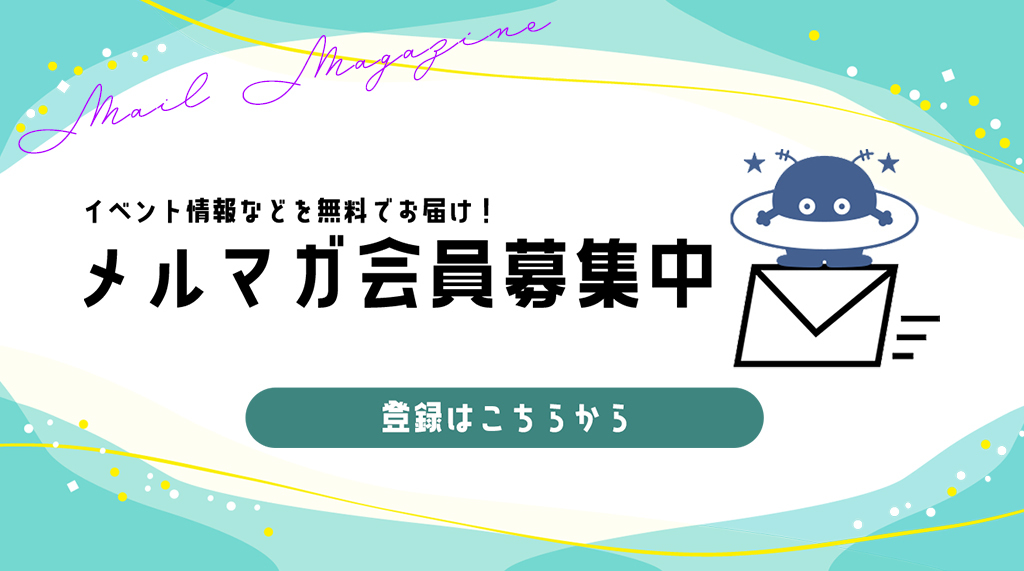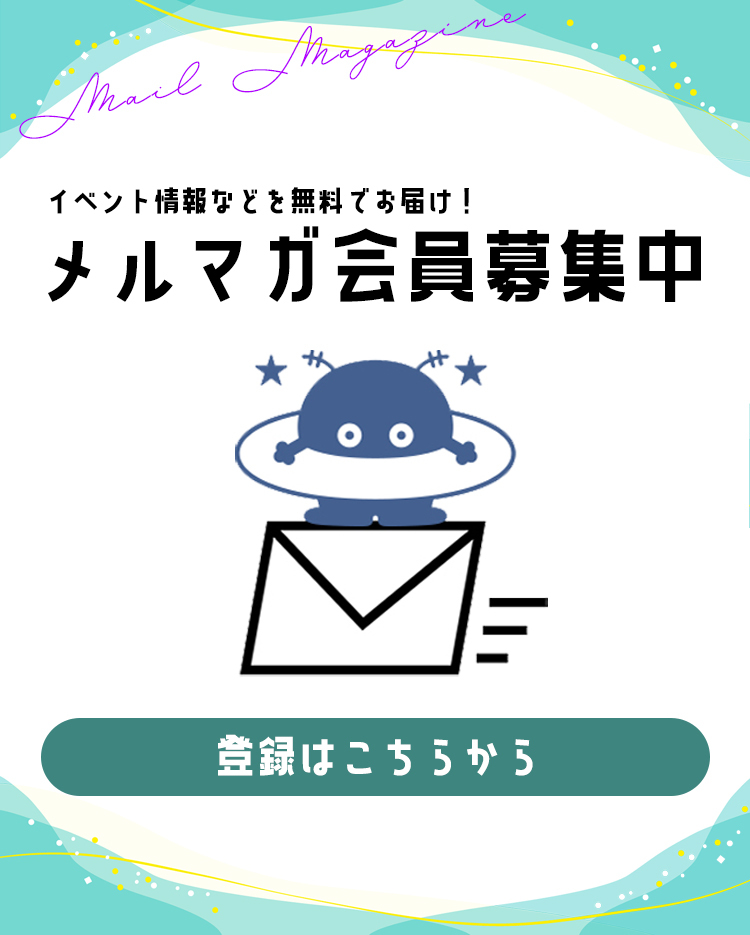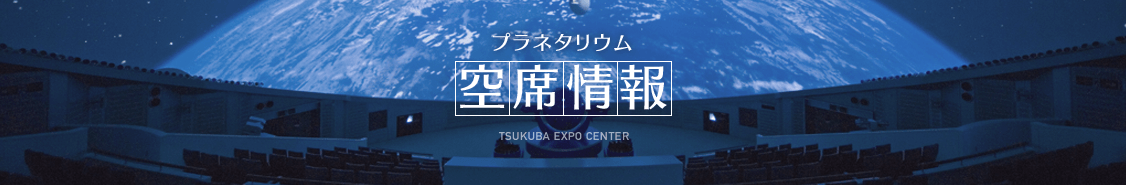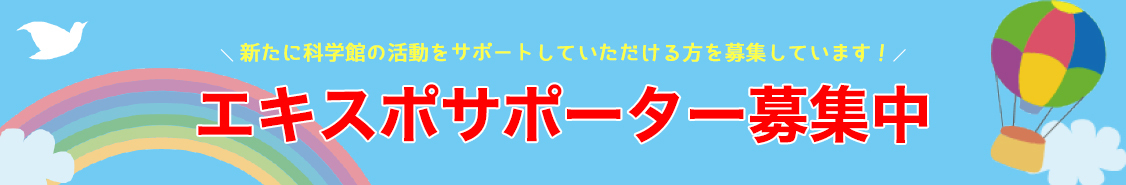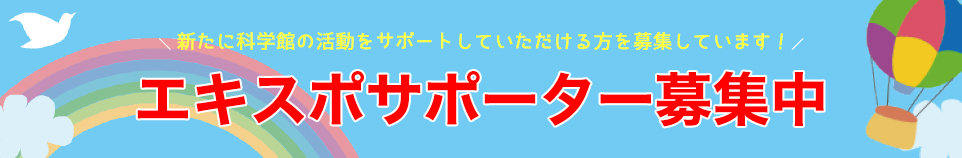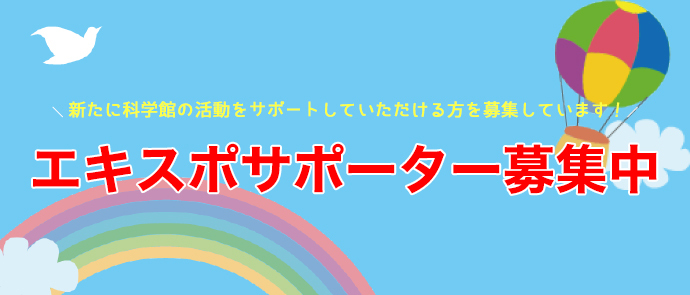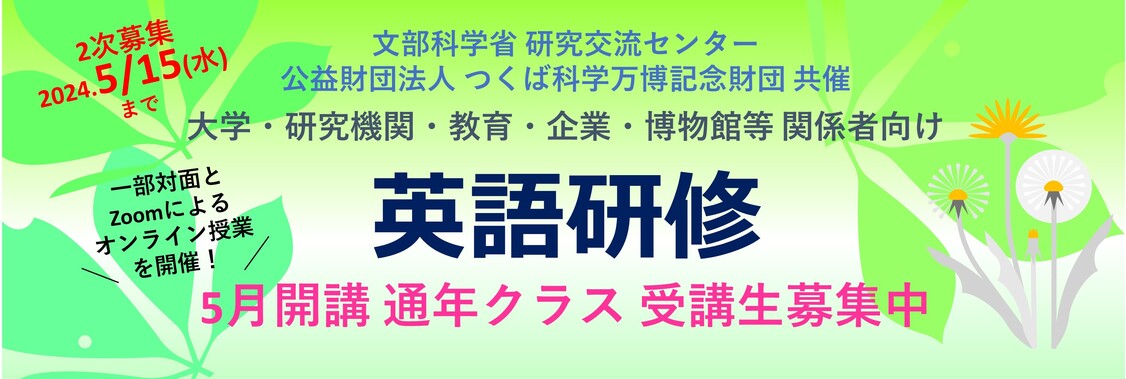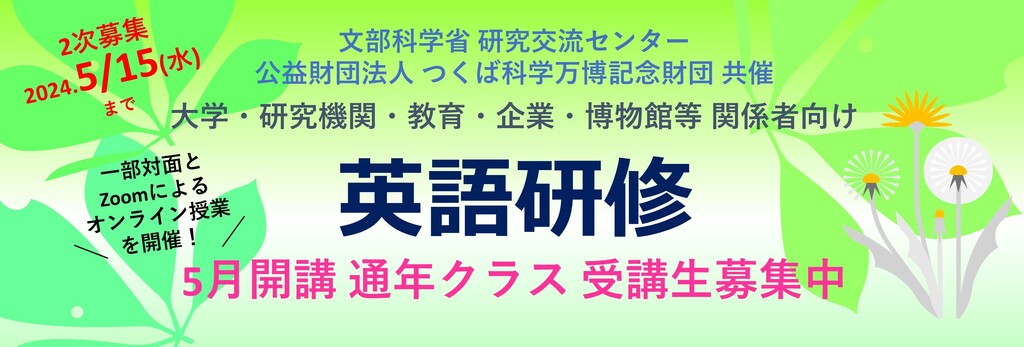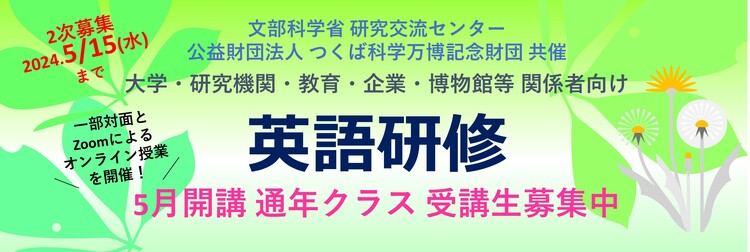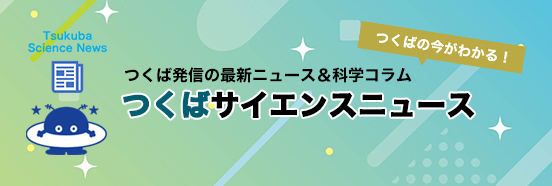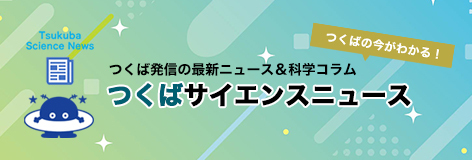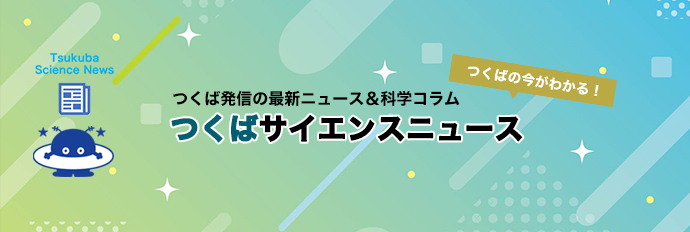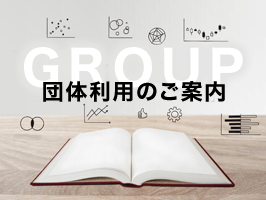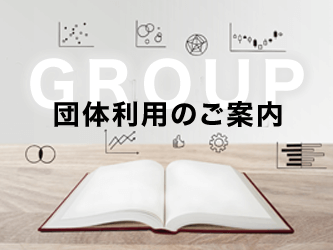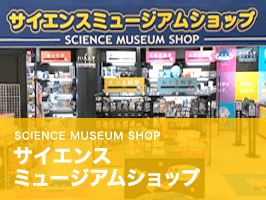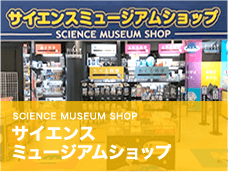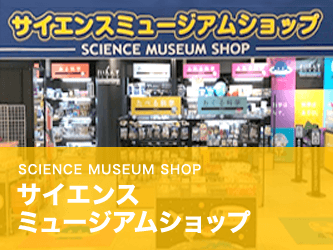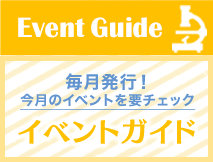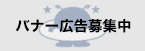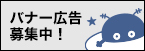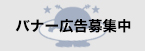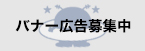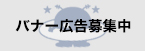- 【重要なお知らせ】
開館カレンダー
新着情報
- お知らせ
- イベント
12月18日
開館日
12月18日
開館日
- プラネタリウム
- イベント
上映スケジュール
プラネタリウム本日上映あり
Now Loading...